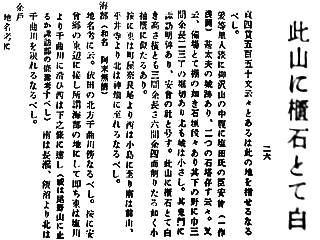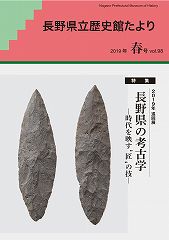|
| 信濃毎日新聞 明治36年1月29日 保科百助「通俗滑稽 信州地質学の話」 |
6月7日は保科百助(1868-1911)の命日、8日は誕生日(旧暦?)です。今も、少しずつですが、知らなかった資料を見ています。
渡辺敏(わたなべ びん 1847-1930)が保科百助について言ったという「一なかるべからず、二あるべからず」という言葉について、バリエーションがあるので集めてみました。
『信濃教育 昭和4年1月』(保科五無斎号)の北村春畦の記事から、明治33年3月頃の出来事として知られていますが、そのときだけではないのかもしれません。(北村春畦の記事は約30年前の回想であり、記憶違いもあるので(明治33年11月の蓼科学校赴任がない 等)、このエピソードもすべてが事実かどうかはわかりません。)
「不可無一、不可有二」は江戸時代から明治時代の辞書類に載っていて使用例も多くあり、特定の出典は意識されていなかったかもしれません。ただ、保科百助は「以」を入れているので(「不可以無一、不可以有二」?)他にも何か参照していた可能性はあるかも。
明治36年1月29日『信濃毎日新聞』 保科百助 「長野高等女學校長渡邊若翁嘗て予を評して曰く、五無齋は奇人なり 縣下以て一なかるべからず、以て二あるべからざる的の人物なりと」
明治42年3月10日『信濃公論』 保科百助 「日本一の小學校長渡邊敏翁嘗つて五無齋を評して縣下以つて一無かる可らず。以つて二ある可らず的の人物となす。」
大正4年11月10日『信濃教育 大正4年11月』 八木貞助 「保科百助君と信州地學」『渡邊敏先生甞て曰く「五無齋の如きもの信州に一無かるべからず。以て二ある可からず。蓋彼は其天禀に得たるものにして、後人の模倣を許さゞるものあればなり。」と以て至言と稱すべし。然して今や此名物男無し矣。』
昭和4年1月1日 『信濃教育 昭和4年1月』 北村春畦 「五無齋研究」「渡邊敏先生は彼が敎育界に於て以て一なかるべからず以て二あるべからずであると答辨せられた。」
昭和5年6月 『信濃教育 昭和5年6月』 八木貞助 「渡邊先生の人格と其反映」「彼の窮措大五無齋保科百助氏の如きも、先生と肝膽相照すものがあつた。先生は五無齋の如きは信州に一あるべく、二あるべからざる人物であると推奨された。他の多くの人々は彼を敬遠したにも關らす、先生はよくこれを容れ、其長處を暢達せしめ、彼の採集した幾千塊の岩石鑛物標本を入るゝ爲に當時多額の資を投じて容噐を提供し、これに校舍の一部を與へて保管し、且これを整理せしめ長野縣地學標本六百組を造つて廣くこれを頒布し、以て天下に信州地學の一般と其材料の豊富なることを周知せしめたる如きも亦特筆すべき事柄ではあるまいか。」
信濃毎日新聞 明治36年1月29日朝刊1面
通俗滑稽 信州地質學の話 五無齋保科百助述
(二)結晶學及び數學との關係
(中略)有体に白状すれば予は普通の礦物學の始めにある結晶學位は兎も角も故理學士菊池安先生の礦物學敎科書中の結晶の部を了解するの能力なし終りに臨み予は世の數學嫌ひの博物學者に一言を呈せん、曰く動物植物の學は兎も角も礦物地質の學は忽ち失敗に終らん、五無齋の研究を斷念して大採集家となりしは全く是れが爲めなり、採集家は五無齋一人にて足れり、長野高等女學校長渡邊若翁嘗て予を評して曰く、五無齋は奇人なり(予は不服なり人間以上のものなれば何ぞ怪物と言はざる)縣下以て一なかるべからず、以て二あるべからざる的の人物なりと、渡邊若翁は稍予を知るものと謂ふ可し、呵々、
信濃教育 昭和4年1月
五無齋研究 北村春畦
(中略)
狸と狢(ムジナ)
これも明治三十三年頃かと思ふ、松本中學長野支校が獨立して、飯田と上田へ新たに中學校の置かれた時である。長野支校の主任島地五六氏は飯田中學校長に、縣視學宮本祐治(※右次)氏は上田中學校長に任命せられた。そこで兩氏の爲め城山館に壯行宴會が開かれたが、盃彈頻りに飛んで宴酣なりし頃、五無齋は談論の行き掛り上、戶野視學官と衝突し風雲將に急ならんとする折しも小林健吉氏は五無齋を拉し去つた。偶々渡邊敏先生が來られて五無齋に代つて其の座へ坐られた、戶野視學官と並んで居た佐柳參事官は憤然として、保科の如き人間が長野縣の敎員間に列して居るのは遺憾である。と云はれたので、渡邊敏先生は彼が敎育界に於て以て一なかるべからず以て二あるべからずであると答辨せられた。所が佐柳參事官は飲みほしたる盃を渡邊敏先生へさしつゝ渡邊君も仲々狸であるわいと戯謔的に云はれた。渡邊敏先生は直に其の盃を飲みほして笑ひながら佐柳さんは流石狢《ムジナ》だけに此の渡邊の狸が見えたわいと、之れ亦戯謔的に云つて返盃された。其の瞬間其の塲に居合せたる春畦は、成程渡邊先生は吾敎育界のオーソリテーであるわい、自分が狸にされながらも遂に談笑の間に對手を狢にしてしまつた、こゝが渡邊先生の老練なる手腕であるとつく/゛\感じた。此の話は聊かレール外ではあるが五無齋の側面觀とするに足る。
渡辺敏と保科百助
https://kengaku5.hatenablog.com/entry/36004932
五無斎保科百助君碑
https://kengaku5.hatenablog.com/entry/36168641
今年の ほしな歌…
歌一つ届かぬ人に思うかな 共に無言歌歌ってほしなと