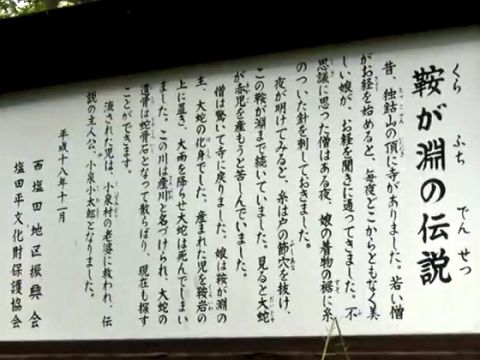|
| 「通俗滑稽信州地質学の話 五無斎復讐心に富む事」(信濃毎日新聞 明治36年1月11日) |
保科百助(1868-1911)「長野県地学標本」製作での"寄付金破約"の経緯は、今も未調査のまま…
避けては通れない話なので、あまり根拠のない推測ですが、書いてみます。
軍への寄付に備えるように、教員に対して指示・示唆があった可能性は考えられないでしょうか。
・日清戦争(明治27年~28年)では、学校で寄付金を取りまとめることが多く行われました。
・採集旅行(明治34年~35年)は、義和団の乱(明治33年~34年)、日英同盟(明治35年1月30日)の頃。日露戦争は明治37年2月~明治38年10月。
・明治34年5月に採集旅行を開始。夏頃(7月~9月頃?)には資金が枯渇したので、破約は5月~6月の頃でしょうか。(「二ヶ月間許りは長野市の某下宿屋に下宿籠城となりたり僅々数円の下宿料にも究するなり」『信濃毎日新聞』明治36年1月11日1面)
・寄付をしたのは師範学校同窓生等で教育関係者。明治34年4月30日の退職広告で上層部に反感を持たれ、協力しないように圧力をかけられた? そのための口実として軍への寄付の準備が利用されたとか…
・標本頒布の募集でも同様の圧力の恐れがあり、その対策として、皇室への献納を行ったのではないでしょうか。(発案が保科百助かどうかはわかりませんが。)
長野県地学標本の寄付金の謎
https://kengaku5.hatenablog.com/entry/30556999
『信濃毎日新聞』明治36年1月11日1面より
通俗滑稽信州地質學の話
五無齋保科百助述
⦅四⦆五無齋復讐心に富む事
孔子《こうし》曰《いは》く怨《うら》みをかくして其人《そのひと》を友《とも》とするは
左丘明《さきうめい》之《これ》を愧《は》づ丘《きう》も亦《また》之《これ》を愧《は》づと五無齋《ごむさい》に
至《いた》つては怨《うら》みある人《ひと》を友《とも》とする事《こと》を好《この》まざ
るのみならず面當《つらあて》に復讐的《ふくしうてき》に一と仕事《しごと》仕事《しごと》
をして見《み》せてやらんと欲《ほつ》するなり前段《ぜんだん》にも
記《しる》し置《お》きたりしが如《ごと》く予《よ》は漫遊《まんいう》の旅費《りよひ》とし
て山禎《さんてい》以下《いか》八九人《にん》の諸君《しよくん》より助力《ぢよりよく》を得《え》て四
百五十圓《ゑん》許《ばか》りの額《かく》に達《たつ》したりければ是《これ》さへ
あればとて大《おほい》に喜《よろこ》び乃《すなは》ち漫遊《まんいう》の途《と》に上《のぼ》りた
り當時《たうじ》予《よ》の心中《しんちう》には口《くち》でこそ四百五拾圓《ゑん》な
れ親子兄弟《おやこきやうだい》の關係《くわんけい》あるに非《あら》ず刎頸《ふんけい》の交《まぢは》りあ
りと言《い》ふにもあらず言《い》はゞ普通《ふつう》一偏《ぺん》の寄附《きふ》
金《きん》や草鞋錢《わろじせん》なり寄附金《きふきん》や草鞋錢《わろじせん》としては少《すこ》
しく巨額《きよがく》なるを感《かん》ず若《し》かず一日《にち》も早《はや》く漫遊《まんいう》
を終《をは》り採集《さいしう》を果《はた》して是《こ》れ等《ら》の人《ひと》に報《むく》ゆると
ころなかるべからずと日毎々々《ひごと/\/\》に金槌《かなづち》を振《ふ》
り廻《ま》はし歩《ある》きたるに標本《へうほん》は愈《いよ/\》集《あつ》まりて愈《いよ/\》
多《おほ》く百種《しゆ》位《くらゐ》にては止《とゞ》まるべくも見《み》えず三百
にも近《ち》かゝらん一日《にち》に一種《しゆ》宛《づゝ》を得《う》るとする
も三百日《にち》を要《えう》すべきに其後《そのご》寄附金《きふきん》は破約《はやく》の
緒《いとぐち》を開《ひら》きたり一昨年《さくねん》の夏頃《なつごろ》は随分《ずゐぶん》究厄《きうやく》に
陥《おちゐ》りたるなり二ヶ月間《げつかん》許《ばか》りは長野市《ながのし》の某《ぼう》下《げ》
宿屋《しゆくや》に下宿籠城《げしゆくろうじやう》となりたり僅々《きん/\》數圓《すうゑん》の下宿《げしゆく》
料《れう》にも究《きう》するなり俸給《ほうきふ》を取《と》り居《を》る身《み》にても
あらば友人《いうじん》を訪《と》ふて借《か》りもしまじを収入《しうにふ》な
き身《み》の金《かね》を借《か》りに行《ゆ》くは返《かへ》すべき目當《みあ》ても
なければ体《てい》のよき乞食《こじき》なり然《しか》らば惡《わ》るロ職《くちしよく》
を辞《じ》して還俗《けんぞく》せんか曰《い》はく否《いな》大《おほい》に否《いな》抑々《そも/\》惡《わ》
る口《くち》の職《しよく》たる何《いづ》れの官省《くわんしやう》よりも辞令《じれい》を受《う》
けたる事《こと》なければ名宛《なあて》を認《したゝ》むるによしなく
名宛《なあて》のなき辞表《じへう》は郵便集配人《いうびんしふはいにん》も大《おほい》に當惑《たうわく》せ
ん然《しか》らば漫遊《まんいう》を繼續《けいぞく》せんか旅費《りよひ》の續《つゞ》かざる
を如何《いかん》せん進退《しんたい》維《こ》れ谷《きは》まりたれども亦《また》つく
/゛\思《おも》ふやう若《も》し此儘《このまゝ》にして打過《うちす》ぎなば世《せ》
人《じん》は予《よ》を何《なん》とか評《ひやう》せん法螺百《ほらひやく》は依然《いぜん》法螺百《ほらひやく》
にして天下《てんか》亦《また》予《よ》と齒《よはひ》せざるに至《いた》らん然《しか》れど
も法螺《ほら》の豫告《よこく》に變《へん》じたる事《こと》歷史上《れきしじやう》其例《そのれい》に乏《とぼ》
しからず新言海《しんぜんかい》に曰《いは》く法螺《ほら》の責任《せきにん》を果《はた》した
るもの之《これ》を豫告《よこく》と云《い》ふ豫告《よこく》なる哉《かな》豫告《よこく》なる
哉《かな》若《し》かず如何《いか》にもして漫遊《まんいう》を終《をは》り採集《さいしふ》を果《はた》
さんにはと例《れい》の山禎《さんてい》に泣《な》き付《つ》き旅費《りよひ》を整《とゝの》え
玆《こゝ》に芽出度《めでたく》二ヶ年《ねん》の漫遊《まんいう》を果《はた》し四百餘種《よしゆ》三
萬餘塊《よくわい》の標本《へうほん》を採集《さいしふ》し終《をは》るに至《いた》りたるなり
是《こ》れ予《よ》が破約者《はやくしや》に對《たい》しての復讐心《ふくしうしん》なり面當《つらあて》
的《てき》行為《かうゐ》なり然《しか》れども予《よ》は今後《こんごは》是等《これら》の諸君《しよくん》に
對《たい》しては感謝《かんしや》の意《い》を表《へう》せねばならぬなり。
そは是《これ》にて寄附金《きふきん》の募集《ぼしふ》すべからざるもの
なること人心《じんしん》の賴《たの》むに足《た》らざるものなる事《こと》と
の眞理《しんり》を發見《はつけん》したり今後《こんご》何等《なんら》の事業《じげふ》を經營《けいえい》
するに當《あた》つても予《よ》はチビ/\したる細《こま》かき
寄附金《きふきん》は募集《ぼしふ》せざるべし他人《たにん》の御影《おかげ》は蒙《かふむ》ら
ざるべし即《すなは》ち今回《こんくわい》破約者《はやくしや》に對《むか》つて發見《はつけん》した
る眞理《しんり》は挙々服膺《けん/\ふくやう》して終生《しうせい》忘却《ぼうきゃく》せざらんこと
を期《き》するものなり然《しか》れども讀者諸君《どくしやしよくん》怨《うら》みも
面當《つらあて》も漫遊《まんいう》を終《をは》り採集《さいしふ》を果《はた》すと同時《どうじ》消滅《せうめつ》し
て跡形《あとかた》もなし五無齋《ごむさい》の心事《しんじ》光風晴月《くわうふうせいげつ》の如《ごと》し